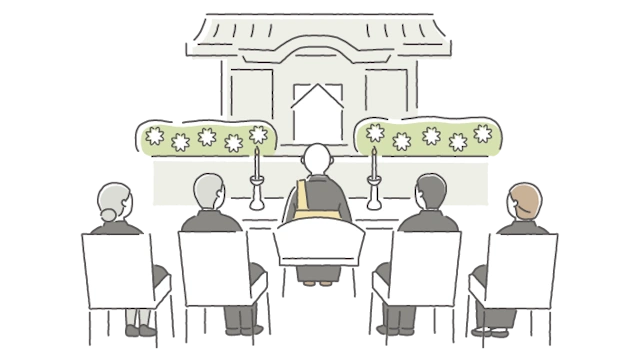葬儀へ参列する際、赤ちゃんも一緒に連れて行っていいかどうか、戸惑ってしまうお父さん・お母さんも多いでしょう。
そもそも葬儀とは人生の最後に行う大切な儀式で、故人に思いを馳せ、遺族にお悔やみや励ましの言葉を直接伝えるための行事でもあります。
葬儀の案内が届いた場合、赤ちゃんがいる方でも、可能であれば参列していただきたいところです。ただし、場合によっては参列を控えたほうがよいケースもあります。
そこで本記事では、赤ちゃんと一緒に葬儀に参列するかどうかを判断するためのポイントと、参列する場合の注意点や持ち物リストについて、詳しく解説します。
参列をお断りする場合のマナーや対処法と、赤ちゃんについてのよくある質問もまとめてご紹介しますので、どうぞ最後までご覧になり参考になさってください。
葬儀に赤ちゃんと参列するかどうかを決める3つのポイント

赤ちゃんと一緒に、葬儀に参列するかどうかを決めるには、次の3つのポイントがあります。
- ①喪主との関係性
- ②喪主や遺族の意向
- ③赤ちゃんの健康状態
①喪主との関係
葬儀の主宰者である喪主との関係性が家族や親族など同じ側の立場で、故人の遺族や親族側に該当する方の赤ちゃんは、葬儀へ一緒に参列しても問題ないため安心してください。
家族や親族ではなく一般参列者の場合は、赤ちゃんの子守りを家族にまかせて本人だけ参列するか、葬儀への参列をお断りして辞退するのが一般的です。
遺族や親族など身内の赤ちゃんなら、周囲も良き理解者が多いため、赤ちゃんがいても和やかな雰囲気で葬儀ができ、親族から手助けやサポートをしてもらえるでしょう。
赤ちゃんがいるという理由で葬儀への参列を諦めてしまうと、後々になって故人や遺族に対して申し訳ない気持ちが込み上げ、後悔しやすい傾向にあります。
もし粗相などのハプニングがあったとしても、遺族や親族、そして自分自身にとっても、いつしか良い思い出になるため、故人のためにもネガティブに考える必要はありません。
ただし、故人と関係のある身内でも、社葬やお別れ会、介護施設や第三者が葬儀費用を負担する場合は、一般的に参列対象外になるため、葬儀の主宰者や喪主に確認してください。
②喪主や遺族の意向
故人の身内ではなくても、喪主や遺族が事情を知っているうえで、「赤ちゃんも一緒にどうぞ」と言われた場合は、ぜひ赤ちゃんと一緒に葬儀へ参列することをおすすめします。
故人と親しかった多くの方が参列することが、ご遺族への慰めや喜びにつながる場合もあります。赤ちゃん連れでの参列も、前向きに考えてみるとよいでしょう。
近年は、家族や親族など少人数で執り行う家族葬が多く行われています。家族葬では、遺族が故人と親しくしていた方をお誘いする場合がありますが、アットホームな雰囲気の葬儀となることが多く、赤ちゃんがいても安心です。
なお、家族葬とは30名以内の参列者を目安とする小さな規模の葬儀形式のことをいい、最新の調査によると、お葬式のうち約半数の50%が家族葬となっています。
| 順位 | 葬儀形式 | 割合 |
| 1位 | 家族葬 | 50.0% |
| 2位 | 一般葬 | 30.1% |
| 3位 | 一日葬 | 10.2% |
| 4位 | 直葬・火葬式 | 9.6% |
参列の依頼を受け、赤ちゃんを連れて行っていいかどうか不明な場合には確認し、遺族や親族の意向を最優先に判断することで、トラブルを回避しましょう。
③赤ちゃんの健康状態
赤ちゃんが生後1ヶ月未満の場合は、葬儀への参列をお断りするのが一般的です。抵抗力の弱い赤ちゃんが体調を崩すことのないよう、安全面を重視します。
生後1ヶ月頃まで、赤ちゃんは体温調節が難しく、免疫機能も発達していません。同様に、産後の体力回復のためには、母体としても外出を控えた方が無難です。
また、生後1ヶ月以上の赤ちゃんの場合でも、母子ともに健康状態に問題がないことはとても重要で、ほかの条件をクリアしている場合でも当日の体調は最優先にしましょう。
一般的にお通夜は17~19時頃から開始されるため、日中との気温差にも気を配る必要があります。
とくに、電車やバスなど、公共交通機関による移動が必要な方はより配慮が必要で、経路の途中で具合が悪くなった場合などは決して無理をしてはいけません。
以上、葬儀へ赤ちゃんと参列するかどうかを決める3つポイントを解説しましたが、連れて行く際は気をつけるべき事項があるため、後述の注意点をよく読んでからお出かけください。
赤ちゃんの事情で葬儀への参列をお断りする場合のマナーと対処法

赤ちゃんの事情により葬儀への参列をお断りする際はマナーがあるため、喪主や遺族へ失礼のないよう、次の4つの手順で対処しましょう。
①葬儀へ参列できないことをきちんと伝える
葬儀への参列をお断りする際は、葬儀の案内が届いたら、最初にきちんと辞退の意志を伝えることが大切です。
電話連絡でも構いませんが、メールやLINEやSNSなどにより、赤ちゃんの事情で葬儀へ参列できない場合のお断りの文例をご紹介しますので、どうぞ参考になさってください。
赤ちゃんの事情で葬儀の参列をお断りする場合の文例
文例では句読点を含めていますが、改まった丁寧な文章にする際は、句読点を省略してください。このたびはご愁傷さまでございます。突然のことにおかけする言葉も見つかりません。本来ならご葬儀へお伺いすべきところ、あいにく幼い子どもがおり参列できずに残念です。〇〇様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
②お香典は郵送するか代理人へ依頼する
葬儀へ参列できない場合でも、お香典は現金書留で喪主へ郵送するか、代理人へ依頼して届けることが可能です。
現金書留でお香典を送る際は、郵便局で現金封筒を購入し、「心よりお悔やみ申し上げます」など、簡単で構いませんので一言メッセージを添えて香典袋に入れたお札を入れます。
代理人へお香典を依頼する場合は、香典袋の左下へ小さく「(代)」(配偶者は「(内)」)と記し、記帳する際には依頼主の名前の下へ「(代)」と書いてもらってください。
③供花を贈る場合は葬儀社へ申し込む
葬儀ではお香典のほかにも、祭壇の周りに飾られる供花を贈ることができるため、希望する場合は葬儀社へ申し込みます。
供花は、家族葬で香典を辞退している場合にも気持ちを伝える手段として適しています。ただしご遺族が、供花や供物も辞退されている場合があるほか、親族の葬儀では、喪主がとりまとめて手配していることもあるため、事前に確認しておくと安心です。
④葬儀後のお悔やみは3日程度してから伝える
赤ちゃんや自身の事情で葬儀に参列できず、何もできていない場合は、葬儀から3日程度経過してから電話や弔問によってお悔やみを伝える方法もあります。
ただし、遺族が弔問をお断りしている場合もあるため、自宅を訪問する際は必ず事前に連絡をして許可を得てから伺い、長居をしないように配慮してください。
遺族が辞退しておらず、葬儀後に贈り物をする場合は、お悔やみの花やお供え物を持参、または郵送すると良いでしょう。
葬儀に赤ちゃんを連れて行くときの7つの注意点

葬儀に赤ちゃんを連れて行くときは、気をつけるべき7つの注意点があるため、手順に沿って解説します。
①喪主や遺族へ許可を得る
いざ葬儀の場面でトラブルにならないように、葬儀への参列に際しては、必ず事前に喪主や遺族や親族へ赤ちゃんを連れて行くことを伝えて許可を取りましょう。
承諾なく赤ちゃんを連れて行くと非常識だと思われてしまう可能性があるため、事前に伝えることが大切です。
②斎場や火葬場の下調べをしておく
葬儀を行う斎場や火葬場については、次のような事項の下調べをしておくと、赤ちゃん連れでも安心して参列できます。
- ・おむつが交換できる設備が整っているか
- ・ミルク用のお湯が出る設備があるかどうか
- ・授乳や休憩できる控室があるか
地域によっても異なりますが、近年の家族葬専用斎場や火葬場では、赤ちゃんや小さな子どものいるご家庭でも安心して参列できる設備が整っているケースもあります。
③ほかの参列者や葬儀社の連絡先を控えてゆとりをもって出かける
葬儀の当日は、喪主や遺族は葬儀の準備や接客応対で忙しいため、親族などほかの参列者の連絡先や葬儀社の連絡先を控えて、時間にゆとりをもって出かけましょう。
葬儀によっても異なりますが、遺族や親族は2時間程度前(一般参列者は受付時間の30分程度前)に到着する必要があるため、万一のときは安全を第一に速やかに連絡してください。
④式場では出入口に近い端の席へ着席する
葬儀中に赤ちゃんが泣いたりぐずったりした場合にすぐに退席できるよう、葬儀スタッフへ依頼して、式場の席次は出入口に近い場所を用意してもらいましょう。
斎場や火葬場によっては、ほかの葬儀の利用者など多くの方々が集うため、あらかじめ周辺をチェックして、赤ちゃんが落ち着ける静かな場所を確認しておくと安心です。
⑤葬儀でベビーカーを使用したい場合は事前に葬儀社へ相談する
葬儀ではベビーカーを使用して参列することも可能なため、希望する場合は事前に葬儀社へ相談してスペースを確保してもらってください。
ベビーカーを使用しない場合は、畳んで邪魔にならない背後や横のスペースへ立て掛けるようにしましょう。
なお、荷物を入れたマザーズバッグは、受付のクロークに預けるのが基本マナーのため、葬儀中に必要な赤ちゃん用品は黒いサブバッグへ入れておくのがおすすめです。
⑥お焼香で赤ちゃんを預ける方へは事前に依頼しておく
葬儀ではお焼香を行わなくてはいけないため、赤ちゃんを抱っこして参列する方は、あらかじめお焼香で赤ちゃんを預けられる方に隣へ着席してもらうよう依頼しておくと安心です。
お焼香は片手でも構いませんが、赤ちゃんを抱っこをしていると、煙が赤ちゃんにかかってしまう可能性があるため、くれぐれも気をつけてください。
⑦葬儀中は音の鳴らないパイル地のおもちゃなどを用意する
葬儀中は振ったり落としたりしても音の鳴らないパイル地のおもちゃや、赤ちゃんがお気に入りのタオルなどを用意すると良いでしょう。
式場によっては、冷え対策なども必要な場合もあるため、事前に確認して赤ちゃんが体調を崩さないようにご注意ください。
葬儀へ赤ちゃんと参列する場合の持ち物リスト

葬儀へ赤ちゃんと参列する場合の持ち物リストをご紹介しますので、どうぞ参考になさってください。
赤ちゃん用品
葬儀に参列する際に必要な赤ちゃん用品は次のとおりです。- ・おむつ・おしり拭き
- ・おむつの処理袋
- ・着替え・靴下など一式
- ・抱っこひもやスリング
- ・粉ミルクや哺乳瓶
- ・離乳食やおやつ
- ・ウェットティッシュ
- ・ティッシュ
- ・タオル
- ・ハンカチ
- ・おもちゃ
- ・ブランケットやおくるみ
- ・ベビーカー
- ・保険証(マイナンバーカード)
葬儀用品
葬儀用品として必要な持ち物は次のとおりで、赤ちゃん用品を入れるためのサブバッグを用意するのがおすすめです。- ・数珠
- ・袱紗(ふくさ)に入れたお香典
- ・ハンカチ
- ・ティッシュ
- ・セレモニーバッグ(男性は不要)
- ・サブバッグ(葬儀中にベビー用品を入れておくと便利)
葬儀に赤ちゃんと参列する際によくある質問

葬儀に赤ちゃんと参列する際によくある質問をまとめてご紹介しますので、気になる項目があればぜひ参考にしてください。
葬儀での赤ちゃんの服装はどうしたらいい?
葬儀だからといって、赤ちゃんに必ずしもフォーマル服を着せる必要はありませんので、目立つ色柄の洋服を避けて、なるべくシンプルな手持ちのベビー服を着せてあげてください。
服装にこだわりたい場合は、黒・グレー・紺・白など、モノトーン系のカラーや、青・水色などの目立ちにくい色合いでコーディネートしてあげましょう。
一般参列者はお香典だけを渡すなら赤ちゃんと一緒に参列してもいい?
葬儀へは参列せず、お香典だけを渡したい方やお焼香だけでもと思う一般参列者の方は、家族など付き添い人へ斎場の傍まで同行してもらって赤ちゃんを預け、本人だけで会葬しましょう。
赤ちゃんを預けていれば、ほかの参列者へも気兼ねなく受け付けをスムーズに行うことができます。
赤ちゃんと1日だけ参列する場合はお通夜と葬儀・告別式のどちらに出席したらいい?
赤ちゃんと1日だけお葬式へ参列する場合、日中の方が安心であれば、2日目の葬儀・告別式へ参列し、火葬場への出棺のタイミングで帰宅しても構いません。
一般参列者の場合、通常はお通夜に参列しますが、同じように葬儀・告別式へ参列しても問題ありませんのでご安心ください。
まとめ:葬儀へ赤ちゃんと参列するかは3つのポイントで判断!連れて行く時は持ち物リストをチェックしよう

葬儀へ赤ちゃんと参列するかどうかを決めるポイントとお断りする際の対処法とマナー、連れて行くときの注意点や持ち物リストについて解説しましたが、まとめると次のとおりです。
- ・葬儀へ赤ちゃんと参列するかどうかを判断する際は、次の3つのポイントに基づいて検討する①喪主との関係性 ②喪主や遺族の意向 ③赤ちゃんの健康状態
- ・葬儀への参列をお断りする際は、葬儀へ参列できないことをきちんと伝え、お香典は郵送するか代理人に持参してもらい、供花は葬儀社へ申し込むが、家族葬では遺族が辞退している場合があるため注意する。葬儀後のお悔やみは3日程度してから伝える。
- ・葬儀へ赤ちゃんを連れて行くときは、次の7つの注意点をチャックする①喪主や遺族へ許可を得る ②斎場や火葬場の下調べをしておく ③ほかの参列者や葬儀社の連絡先を控えて時間にゆとりをもつ ④式場では出入口に近い端の席へに着席する⑤ベビーカーの使用は事前に葬儀社へ相談する ⑥お焼香で赤ちゃんを預ける方へは事前に依頼する ⑦葬儀中は音の鳴らないおもちゃを用意する
弘善社は北海道旭川市・北見市・網走市にてご遺族や参列者の方が快適に過ごせる斎場を運営しております。
参列者の皆様に安心してご利用いただけるよう、葬儀のサポートをしておりますので、赤ちゃん連れのご利用者様で心配事やお悩みがございます際は、どうぞお気軽にご相談ください。