看取りとは、どのようなことをいい、具体的にどのようなケアをするのか、よく分からない方もいらっしゃるでしょう。
死期が迫った方の介護をする看取りとは、家族や近親者ができる人生最期の恩返しです。真心を込めて介護をしたいものですね。
そこで本記事では、看取りに関して、意味や役割、看取りケアを始める流れなどの基礎知識と、具体的に看取り介護で必要なケアについて詳しく解説します。
看取りケアとよく似た用語の「ターミナルケア」や「緩和ケア」との違いや、看取りでよくある質問までご紹介しますので、どうぞ参考になさってください。
看取りとは何か?
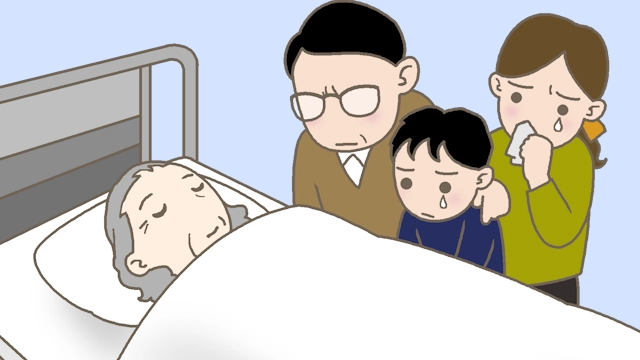
看取りとはどのような意味や役割があるのか、まず基本的な知識について解説します。
看取りの読み方と意味とは?
看取りとは、「みとり」と読み、加齢による老衰や病気によって、寿命を迎える方の人生最期に立ち会い、臨終の瞬間を見届けることをいいます。
亡くなる前の終末期のお世話は、「看取りケア」や「看取り介護」とも呼ばれ、介護士や家族によって行われるのが一般的です。
看取りの役割とは?
看取りには、本人の意思を尊重し、人としての尊厳を保ちながら、終末期を穏やかに過ごせるようにサポートする役割があります。
人生の質となるQOL向上を目指すことが最大の目的のため、看取りケアでは、無理な延命治療を行いません。
看取りケアや看取り介護に携わる介護士は、対象者の心身の苦痛を和らげるケアを行うほか、ご家族の負担を軽減し、精神的な支えとなる役割も担っています。
看取りにおける最新状況
医療業界や介護業界の進歩により、近年は病院や介護施設で亡くなる方が増えている傾向にあります。
かつては、医師による診断のもと、長男の妻や長女などの家族が高齢になった親の介護ケアを行い、自宅で看取ることが一般的でした。
しかし現在は、少子化や共働き、価値観の変化などに伴って、医師・看護師が介護士や家族と連携して、看取りケアを行うケースが増加しています。
最新の調査結果によると、日本人が亡くなる場所として最も多いのが病院・診療所で、続いて、自宅、介護施設・老人ホームの順となっています。
| 死亡場所 | 割合 |
| 病院・診療所 | 65.7%(1,035,528人) |
| 自宅 | 17.0%(267,335人) |
| 介護施設・老人ホーム | 15.5%(244,692人) |
| その他 | 1.8%(28,461人) |
出典:人口動態調査 人口動態統計 確定数 死亡 年次 2023年(政府統計の総合窓口)
看取りの重要性
死亡数が増加して人口減少が加速する「多死社会」を迎える日本では、慢性的な病床不足が懸念されており、病院以外の自宅や介護施設における看取りの強化が課題となっています。
実際、コロナ禍においては、日本各地の病院で病床不足が生じて、新たな病人の受け入れが困難となる事態に陥りました。
本人の意思が確認できない万一のとき、延命治療の有無や、看取り介護の方針は、家族が決定しなければならないため、家族にとって責任の重さを感じるケースは少なくありません。
さらに、孤独死は大きな社会問題で、最新の調査によると、一人暮らしの自宅死は約7万6千人に及び、そのうち死後8日以上経過して発見された孤立死は約2万2千人を占めています。
出典:令和6年中における警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者について(警察庁)
| 性別 | 平均寿命 |
| 男性 | 81.09歳 |
| 女性 | 87.13歳 |
どんなに医療が進歩しても、上記のように人には寿命が訪れるため、自分の終末の在り方や看取りについては、生前のうちに検討や対策をしなければいけない課題といえるでしょう。
看取りケアを始める流れ

看取りケアの基本的な流れは、次の5つのステップとなります。
- ①本人の意思や家族の意向の確認
- ②地域包括支援センターへの相談
- ③介護チームの編成
- ④ケアプランの作成
- ⑤介護用品の準備や環境整備
①本人の意思や家族の意向の確認
終末期を迎えるにあたって、自宅や介護施設などの場所や延命治療の有無などの医療について、本人と家族で話し合って、意思を確認し合います。
ここで注意したいのは、半数以上の高齢者が自宅で最期を迎えたいと希望しているのに対して、実際に実現できている方の割合は、2割未満に留まっているという実態です。
出典:高齢化の状況(内閣府)
看取り介護は、特に高齢の配偶者や、離れて暮らす子供にとって負担になりやすいため、家族でよく話し合い、まずは課題や問題点を明確にしましょう。
②地域包括支援センターへの相談
本人が居住する地域にある「地域包括支援センター」へ相談して、必要な介護サービスや支援に関して、アドバイスを受けます。
地域包括支援センターへの相談は無料です。対面による相談は予約が必要な場合があるため、先に電話で問い合わせてからお出かけください。
スムーズに充実した打ち合わせを行うためには、事前に不安や困っていることをリストアップして、メモを取りながら相談するのがおすすめです。
③介護チームの編成
地域包括支援センターで、看取り介護に必要なケアマネジャーや医師・訪問看護師などの専門家を紹介してもらい、チームを編成します。
看取りで必要な24時間体制の医療・介護サービスに対応できるよう、事業者の紹介や、要介護(要支援)認定の申請手続きなどをサポートをしてもらいましょう。
地域包括支援センターには、保健師・社会福祉士などの専門スタッフも配置されているため、日常生活での悩みなども相談できます。
④ケアプランの作成
ケアマネジャーによる分析に基づいて、本人の意思や家族の意向を盛り込んだケアプランを作成します。
ケアプランとは、利用者一人ひとりの心身の状態や生活環境、本人や家族の希望に合わせた介護サービスの計画書のことをいいます。
介護サービスはケアプランに則って提供されるため、気になることがあればケアマネジャーへ相談して、改善してもらうことや、家族が設計することも可能です。
⑤介護用品の準備や環境整備
ケアマネジャーへ相談のうえ、介護用品の準備や介護リフォームなど、必要に応じて看取り介護の環境を整えます。
看取りで使用する介護用品には、介護ベッド・床ずれ防止用具・排泄ケア用品・清拭用品・見守りカメラ・衛生用品(マスク・グローブ・介護用シーツ)などがあります。
介護保険を活用することで、さまざまな介護用品のレンタルやサービスを利用できるため、あらかじめ適用される準備や給付金について調べておくと安心です。
看取りケアとターミナルケアや緩和ケアとの違い

| 種類 | 特徴 |
| 看取りケア | 死期が迫っている人への食事や排泄などの日常生活の介護 |
| ターミナルケア | 死期が迫っている人への点滴などの終末期医療や看護 |
| 緩和ケア | がんなど生命に関わる疾患における苦痛な症状への緩和措置 |
看取りケアと、ターミナルケア(終末期ケア)や緩和ケアとの大きな違いは、日常生活の介護を主体にするのか、医療行為を主体にするのかの違いにあります。
看取りケアの特徴
看取りケアの大きな特徴は、基本的に日常生活の介護を主体にするため、介護施設や自宅でもケアができ、家族でも対応できることです。
これに対して、ターミナルケアや緩和ケアは、病院やホスピス、医療機関と連携している介護施設など、医師による措置や訪問看護が積極的に行われます。
ターミナルケアの特徴と看取りケアとの違い
ターミナルケアとは、終末期ケアとも呼ばれ、看取りケアと比較すると、医師との連携による医療処置が多い傾向があります。
一方で、看取りケアは、日常生活のお世話が中心となり、必要に応じて医療措置が施される点が大きな違いです。
緩和ケアの特徴と看取りケアとの違い
緩和ケアとは、がんなどの生命に関わる疾患のある患者に対して施される心身の苦痛を和らげるためのケアのことをいい、看取りケアと同じように、QOL向上を目指すための支援です。
緩和ケアが時期や病状を問わないのに対して、看取りケアは、人生の最終段階に特化したケアであることが大きな違いといえます。
看取り介護で必要な10のケア

看取り介護で必要なケアは、大きく分類すると次の3つですが、具体的に10種類のケアがあるため、その内容について、詳しく解説します。
- ・身体的ケア
- ・精神的ケア
- ・家族へのケア
身体的ケアとは?
身体的なケアとしてやることは、具体的に次のような内容となります。
- ①日常生活のサポート
- ②清潔感の維持
- ③苦痛の緩和
- ④安楽な姿勢の保持
①日常生活のサポート
看取りケアでは、日常生活のサポートとして、食事・水分補給・着替え・排泄などにおける介護を行います。
②清潔の保持
死期が迫り入浴が難しい方の看取りケアでは、温かいタオルで身体を拭く清拭(せいしき)や、足浴・手浴などによって、清潔を保持します。
③苦痛の緩和
痛みや呼吸困難などによる苦痛を和らげるため、マッサージや酸素吸入など、症状を緩和するための処置を行います。
④安楽な姿勢の保持
床ずれを防ぐための寝返りや、体や呼吸が楽になる姿勢を保ち、快適に過ごせるようにサポートします。
精神的ケアとは?
精神的なケアとして行うことは、具体的に以下のような内容です。
- ⑤不安や孤独感の軽減
- ⑥快適な環境の提供
- ⑦意思の尊重と希望の実現
⑤不安や孤独感の軽減
死期が迫ると、死への恐怖や孤独感に襲われやすいため、看取りケアでは一人にしないように配慮し、声がけや手を握るなどして、不安を軽減できるように寄り添います。
⑥快適な環境の提供
看取りケアでは、快適な環境づくりも大切です。採光や換気に配慮し、リラックスできる音楽を流したり、癒される花や本人が好きな物を飾るなどの工夫を行います。
⑦意思の尊重と希望の実現
本人の意思を尊重して、希望に沿ったケアや、思い出作りのサポートをしたり、葬儀・お墓・相続などの終活に関する支援を行うケースも多くあります。
家族へのケアとは?
看護や介護に従事する方が家族へのケアとしてやることは、具体的に次のような内容となります。
- ⑧情報共有と相談対応
- ⑨肉体的・精神的サポート
- ⑩終活の支援やグリーフケア
⑧情報共有と相談対応
介護施設などに看取りケアを委ねると、本人の状態や日々の変化を記録して、情報共有が行われるほか、家族からの質問や相談に対応してもらえます。
⑨肉体的・精神的サポート
家族の代わりに介護士に看取りケアを行ってもらうことで、家族の肉体的な負担が軽減されます。さらに、介護の指導も受けられ、精神的な支えにも繋がります。
ここまで⑩終活の支援やグリーフケア
施設や介護士によっては、生前のうちから葬儀社や納骨先の選定をサポートします。
また、本人が亡くなった後も、遺族が悲しみから立ち直れるよう、ケアを行う場合もあります。
看取りに関してよくある質問

看取りに関してよくある質問をご紹介しますので、気になる項目があればチェックしておくと安心です。
看取り期間はどのくらい?
看取り期間には個人差があり、体の状態や治療状況、環境や介護体制などによって、数日から数ヶ月と幅広い期間となっています。
たとえば末期がん患者の場合、最期の3日間で自宅に戻り、家族が看取る事例もありますが、余命1週間程度と予測される場合でも、自宅に戻ってから急変を起こすケースもあります。
自宅で看取ることのメリット・デメリットとは?
自宅で看取ることにはメリットとデメリットがあります。短期間の自宅での看取りケアの場合、家族への負担を軽減しやすい傾向にあります。
メリット
- ・本人にとって住み慣れた環境で、快適さや安らぎを感じられる。
- ・本人の寂しさを軽減でき、家族と過ごせることに喜びを得られる。
- ・介護する方の安心感や満足度が高まり、死後も達成感を感じられる。
- ・本人と家族にとって臨機応変な介護ができ、最期の思い出づくりがしやすい。
- ・家族が介護の知識と経験を得られる。
- ・親族や本人の友人・知人などが日時を問わずに訪れやすい。
- ・入院費や居住費がかからないため、入院や介護施設と比較して費用負担を抑えやすい。
デメリット
- ・家族の身体的な負担が大きくなり、長期化すると疲労が蓄積してしまう。
- ・家族の拘束時間が長く、思うように外出ができなくなってしまう。
- ・介護や死を目前にすることで、家族が精神的なダメージを受ける場合がある。
- ・疲労やストレスから、本人に対して嫌悪感を抱いてしまう場合がある。
- ・緊急時に速やかな医療処置を施せない場合がある。
看取り介護について学ぶ方法は?
介護未経験者でも専門資格取得講座や研修会に参加することで、看取りについて本格的に学ぶことができます。
また、看取りに関する資格制度として、次のようなものもあります。
- ・終末期ケア専門士(一般社団法人日本終末期ケア協会(JTCA)): 職種により2年または3年以上
- ・看取りケアパートナー(一般社団法人みんなのプライド):未経験可
- ・看取り士(一般社団法人日本看取り士会): 未経験可
まとめ:看取りとは人生最期の恩返し!本人と家族のために10のケアを大切にしましょう

看取りについて、意味や役割の基礎知識、看取りケアを始める流れ、看取り介護で行うケア、ターミナルケア・終末ケアとの違いについて解説しましたが、まとめると次のとおりです。
- ・看取りは、人としての尊厳を重視し、本人の希望や家族の意向に沿った場所や内容で介護ができるように、ケアプランを考案して計画的に行う。
- ・看取りケアは、医師と連携するターミナルケアや、苦痛を軽減する緩和ケアと異なり、介護士や家族が行うことができる。
- ・看取り介護では、次の10のケアが必要。身体的ケア(①日常生活のサポート ②清潔感の維持 ③苦痛の緩和 ④安楽な姿勢の保持)、精神的ケア(⑤不安や孤独感の軽減 ⑥快適な環境の提供 ⑦意思の尊重と希望の実現)、家族へのケア(⑧情報共有と相談対応 ⑨肉体的・精神的サポート ⑩終活の支援やグリーフケア)
終末医療や看取りは、家族にも関係する大事な課題のため、できるだけ早いうちに家族会議を行い、正しい知識を備えて、方針を決めておくことが大切です。
弘善社では、北海道旭川市を中心に、生前の終活から葬儀、納骨、死後に必要な手続きなどのお手伝いを行っています。
葬儀に関しては、介護施設やご自宅へのお迎え、在宅介護の方の自宅葬にも対応しており、ご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にお問い合せください。







